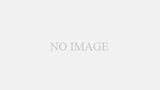売掛金の回収、逆から見れば買掛金を支払う場合、たいていは銀行振込です。振込の際には、振込手数料が発生する場合がありますが、振込手数料はそもそもどちらが負担すべきものなのでしょうか?
本記事では法的な見解を提供するものではなく、あくまで実務上の慣習と経緯を整理したうえでの情報提供を目的としています。したがって、特定の立場を支持したり批判したりという意図はありませんので、その旨ご理解いただける方のみ御覧ください。

一般的には受け取り側の負担(とされていたが)
振込手数料を支払側、受取側のいずれが負担するかは商法上の取り決めはありません。(厳密に言えば、債権持参の原則という民法規定があるのですが、現代の商習慣になじまないもので、当事者間の合意で負担者を決める・慣習で決めるというのが一般的でした。)
ですから、どちらが負担しても良いですし、支払側が負担する場合もあれば受取側が負担する場合もあります。
受取側負担の根拠
一般的な感覚や商慣習としては「受取側」が負担することが多いようです。
受取側が負担する根拠としては、請求をした受取側が代金を回収する義務があるので、受取側が負うべき「代金の回収にかかるコスト」(交通費・人件費etc)を節減できたから、ということです。
家賃などになると支払側が負担することも多いようですが、この辺りは、取引における当事者の力関係などでも変わるようです。
会社によっては、一定の金額以上であれば受取側が負担するが、金額が少額であれば、相手に負担して欲しい旨を請求書などに書いてあるところもあります。
税理士報酬は
税理士報酬は、顧問契約に基づいて毎月、銀行引き落としが一般的です。
銀行引き落としとなると、受取側が収納会社(引き落としを代行する会社)を利用して代金を回収していることとなり、振込手数料を負担していることと変わりません。
世の中の取引を最も多く見ている税理士の報酬が、受取側の負担なので、「振込手数料は受取側負担」という慣習が一般的だと思います。
私見として(補足)
この記事を執筆した当初の2010年代は、商慣習で受取側負担が優勢だったように思います。
ただ、消費税におけるインボイス制度の導入に伴って、「インボイスに記載されている金額」と「取引で動かした金額」(つまり振込額)に齟齬があると、取り扱いがややこしく煩雑になります。
そのため、2020年代に入ってから、民法における「持参債務の原則」が原則なので、支払者が負担という論調が多く見られるようになりました。
取引当事者間での合意があれば、その合意が優先されます。したがって、受取人負担という慣習が広く共有されていれば、それが個別契約に準じて扱われる場合も少なくありません。
なので、かつては商慣習として受取人負担が優勢だったが、インボイス制度による処理の煩雑さを緩和するなどの目的と合わさって、現代は支払側負担とする方も増えてきた、というのが実態に近いと思われます。
振込手数料の会計処理(売掛金)
振込手数料の会計処理は、いくつかの処理方法がありますが、一般的なものをご紹介します。
売掛金50,000円を振込料550円当社が負担して普通預金で回収した場合はこうなります。
(入金のタイミングで、売上を上げている会社は、売掛金でなく「売上高」ですが仕訳のかたちは同じです)
普通預金 49,450 / 売掛金 50,000
支払手数料 550 /
この場合、預金通帳には、49,450円が記載されるので、上記の仕訳のように修正しないと、売掛金と入金額の差額が溜まってしまいます。(複合仕訳となりますので、利用のシステムに沿った修正が必要となるでしょう)
先方(支払側)が負担してくれた場合には…
普通預金 50,000 / 売掛金 50,000
となるので、請求書の金額と入金額が一致しますから特に先ほどのような修正は不要です。また、このパターンは売掛金だけでなく債権の回収全般にも応用できます。
振込手数料の会計処理(買掛金)
買掛金50,000円を振込料550円先方負担で、支払った場合はこうなります。
買掛金 50,000 / 普通預金 49,450
/ 支払手数料 550
振込手数料が貸方に出てくるので違和感もありますが、借方で同額が出ているはずなので、プラマイゼロです。
つまり、上記の仕訳のあとに
支払手数料 550 / 普通預金 550
という仕訳があるので、支払手数料が貸借同額になって消える→自社は負担していない(先方が負担した)ということです。
当社が負担の場合は、
買掛金 50,000 / 普通預金 50,000
支払手数料 550 / 普通預金 550
となり、特に迷うことはありません。
※おそらく、2020年代以降、急速に支払側負担の風潮が強まったのは、上記のように支払者負担のほうが経理システム的に簡便だという理由がかなり大きいと思われます。
実務的な余談
こんな厚かましい人もいました
請求を受けた代金を、勝手に分割にして払うような人がいます。
たとえば、500,000円の買掛金を、勝手に分割して払ってくる。100,000円×5回とかで払う。
さらにその都度、振込手数料を相手負担にする。
一回あたりの振込手数料が、500円ほどだとしても5倍になれば2,500円。
相手からすれば、非常に迷惑ですね…
こんな人がいると、確かに支払者が負担するという主張をしたくなるというのもわからなくはありません。(こんな人、滅多にいないですけど)
トラブル防止の観点から
先にも少し触れましたが、インボイス制度の導入に際して、「持参債務の原則」を引き合いに出して、商慣習的に行われていた「受取人負担」を、一方的に「支払者負担」に改めようとするのは、少々乱暴かもしれません。
どちらにも言い分はありますし、受取人負担だとインボイス制度における事務が煩雑だというのも理解できます。(現状では特例の適用により、特に追加のインボイス処理が不要とされるケースが多いようです。)
トラブル防止の観点からも、今後は契約書や請求書にどちらが負担すべきなのかを明記することが、より重要になるかと思われます。