「社会保険料は決められた金額を払うもの」と思考停止していませんか?
設計段階で余裕のある金額に設定できていれば、資金繰り破綻のリスクは大きく下げられます。
実際に破綻に陥った事例を紹介しますので、反面教師として対策にお役立てください。
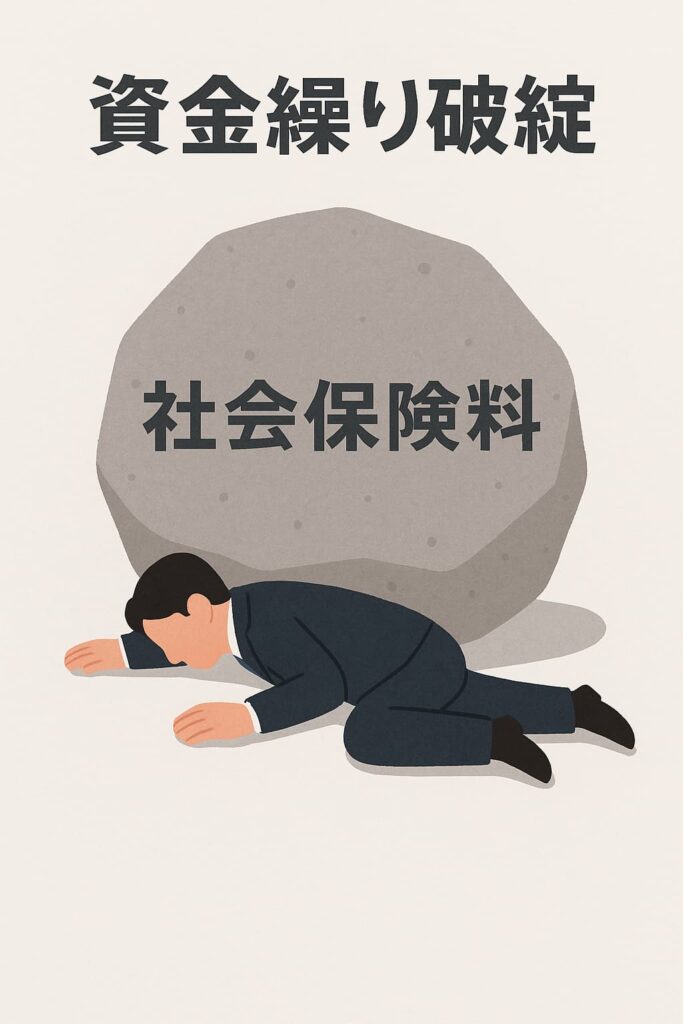
なぜ社会保険料は中小企業の資金繰りを圧迫するのか?
社会保険料は極めて大きな固定費であるため、中小企業の資金繰りに与える影響が非常に大きいです。
どのくらいの大きさかといえば、給料(実際には標準報酬月額)の約15%、従業員も同額を負担して翌月末に支払います。
つまり給料総額が100万だと、会社と従業員がそれぞれ15万ずつ負担して、翌月末に30万をまとめて会社が支払うこととなります。
大きな金額であるため、その金額を主体的にコントロールしないと、資金繰りを圧迫してしまいます。
社会保険料で破綻した実例
誤った人件費設計が招いた社会保険料破綻の実例
売上や経費の予測など、事業計画が杜撰なまま役員報酬と従業員の給料を設定。
売上が変動しても払える役員報酬額でなく、欲しい金額を設定し、社会保険労務士もそれを鵜呑みにして、社会保険の手続きをしました。
結果として、会社の財政には不相応な社会保険料となり、売上は目標には到達しないものの、それなりに上がっているにも関わらず、社会保険料の負担が重くのしかかりました。
社長も危機感もなければ、まだ責任感もなく、タイミング悪く業績も悪化してしまい、社会保険料を滞納してしまいます。
改善の先送りで“差押え”に──経営判断の遅れが命取り
起死回生の策として、手を尽くして融資を受けたのですが、融資で得たお金も滞納した社会保険料の納付に消えてしまい、資金繰りはずっと苦しいままです。
資金繰りを改善するには、人件費を削減するほかありませんから、弊社としては「役員報酬の減額」「雇用の削減」「一部業務は外注化」などを新たな事業計画とともに提案しました。
しかしながら、ズルズルと決断を先延ばしにして、手をこまねいているうちに滞納していた社会保険料が差押えられてしまいました。
なぜ社会保険料問題は資金繰り破綻に直結するのか
毎月数十万円が資金を圧迫──社会保険料の負担感
水道光熱費や広告宣伝費のように、使わなければ支払いが生じない、あるいは売上が下がれば支払いが減る、という性質のものでありません。
コントロールするという主体的な意志がない(先の例のように不相応な社会保険料を何も考えずに設定する)と、大きな金額を固定的に支払続けることになります。
社会保険料の滞納が“信用失墜”に直結
社会保険の徴収は厳しいルールで運用されており、逃れられません。
そのうえ、滞納すると信用問題となります。
社会保険料の滞納するような会社は、他の支払も滞納しがちですし、そうなれば社会保険事務所だけでなく、税務署や銀行などからも、「要注意」とみなされます。
突然の差押えで資金繰りが即死する
滞納が常態化すれば最終的には差押となります。
差押は基本的に、いつあるかは予測がつきませんから、突然に預金口座からお金が消えています。
社会保険料を滞納しているくらいだから、そもそも預金通帳に余裕はないことが多いため、差押されると残高が無く、ほかの支払いも困難になります。
打開しようにも、社会保険料を滞納するような会社は、融資など望むべくもありませんので、金策はほぼ不可能。文字通り、資金繰りはほぼ即死です。
滞納を防ぐ3つの対策
合法的に社会保険料を下げるには?標準報酬月額の見直し方
会社が潰れそうなのに、給料を下げたり雇用を縮小したりができない社長がいますが、手をつけないと潰れますから、やらざるを得ないでしょう。
社会保険料の計算は、社会保険用の給料(標準報酬月額)を決めて、これに率をかけて算定していますから、正当な手続を踏んで、変更すれば合法的に社会保険料は下げられます。
要するに減給です。ただし、即座に社会保険料は下がらず概ね3ヶ月程度のタイムラグがありますから、早め早めに動かないと、間に合いません。(引下げてから3ヶ月を経過した段階で「月額変更届」を提出します)
外注化による固定費削減(注意点あり)
人件費の削減には、雇用を減らす必要があります。
雇用を減らすには、法的な壁もありますから、慎重に対応せねばなりませんから、会社設立当初から、必要最低限しか雇用せず、外注さんに協力してもらうなど設計を工夫する価値はあります。
従業員だった人を外注化・業務委託化するのは、不可能ではありませんが、偽装請負の問題もあり、さまざまな法的な問題をクリアしなければならず、さらに慎重な対応が必要です。
役員報酬の戦略的な管理
法人税法の制約から金額変更は難しい役員報酬ですが、業績悪化ならば変更可能です。
とはいえ、役員報酬を下げると、いざというときに社長が会社にお金を貸すことができない事態に陥ります。
業績が回復するかもしれないし、役員報酬を期中で下げるというのは、それなりにハードルもありますから、セーフティにいくならそのままでいって、未払にしておき決算のタイミングなどで精算するというのもアリでしょう。
いずれにせよ、資金繰りも税金の納税も、そして税金の納税と密接な関係にある役員報酬も、一旦後手を踏むと半永久的に後手を踏み続けることになりますから、常に先手を取れるよう計画的に対処することが重要です。
本質的には「経理無関心」が最大のリスク
社長が経理に無関心だと、社会保険料の問題に気づかないままです。
気づいたときには、もう取り返しがつかないことになっています。
経理担当者がいない会社ほど、社長の関与(作業をするということでなく関心を持ち、勘どころを押さえておく)が不可欠です。
【まとめ】
・社会保険料は極めて大きな負担
・後手を踏まないように設計段階で主体的にコントロールを
・滞納=即信用失墜。取り返しのつかない損失になる。
・経理に無関心であることが、最も根本的な要因



