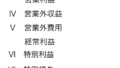税金の納付書など、きれいな数字を記入する必要がある書類では「数字のテンプレート(定規)」が便利です。
最近では電子納税が普及し、手書きの機会は減っていますが、それでも紙の納付書や申請書を扱う場面は完全にはなくなっていません。
本記事では、テンプレートの使い方や注意点を紹介します。
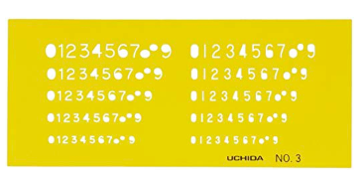
手書きを避けたい理由とは
個人的には手書きの書類は好きではありません。時間がかかったり、書き損じのリスクがあったり、手書き故に汚かったりするからです。
ただ、そうも言っていられません。
経理事務をやっていると、源泉所得税の納付書や、国税、地方税の納付書、労働保険の申告書等に数字を書く機会があります。
すべてをインターネット上で処理できればよいのですが、そういうわけにもいきません。様々な事情から手書きすることもあります。
汚い文字はNG:テンプレートの出番
汚い(もう少し言い方を柔らかくすると読みづらい)数字や文字は、よろしくありません。
事務職たるもの、誤解を与えるというのはタブーですので、読みづらい数字や文字を書くというのは許されません。
とはいえ、字が一朝一夕にうまくなるというものでもないので、ペン習字に通ってる隙がないのであれば、数字のテンプレート(数字の定規)を使って字を綺麗に書くというのも一つの方法ではあるのかなと。
税金の納付書や労働保険の申告書など、機械で数字を読み取る(OCR)書類に数字を書く場合には、数字テンプレート(数字の定規)をあてて使えば、同じ字を書くことができます。
もし、数字が汚いと悩んでいる方がいれば、数字のテンプレートを是非お使いください。
テンプレートのデメリット:時間がかかる?
書類にテンプレートをあてて、ボールペンでなぞれば、テンプレートの数字がそのまま書けるのですが、「6」「8」「9」などは、書きづらいのでちょっとしたコツが必要です。
コツと言ってもそんなに大したことでなく、数字の書き順を無視してなぞりやすいように書いていくというだけですが。
フリーハンドで書けば5分もかからないような書類も、これを使えば倍以上の時間がかかります。
さらに、数字をなぞることに熱中しすぎて書き損じるリスクも上がります。
ですから、利用の際には下書きやお手本を作っておいて、それを見ながら書くのが最も確実です。
下書きやお手本を作ってから核となると、更に時間がかかってしまいます。
そう考えると、紙の書類はなるべく使いたくないというのが本音となってしまいますが、最初に述べたように紙の書類でやらざるを得ない場合もあるので、数字のテンプレートの需要もまだまだあるのではないでしょうか。
効率化の観点ではやや非合理?
(経理)事務を効率化するという観点からは、好ましい道具ではないかもしれません。
ただ、様々な制約からインターネット上で処理できない場合もあります。そういった場合には、紙でやったほうが精神衛生上いい場合もありますので、柔軟に対応すればよいのではないでしょうか。
ちなみに、源泉所得税の納付書などはインターネット上で処理できます。
近年は、税金の納付書も利用される方が減ってきており、電子納税の利便性も認知が高まっているのかと思います。体感的には、テンプレートをあてて納付書を作成する時間が10分くらいだとすると、インターネットを介して電子納税手続きを取るほうがやや早いと感じています。
金融機関まで実際に足を運ぶ手間を考慮すれば、ここの効率化は大きな価値があると思いますので、これを機にインターネットを介しての支払を検討してみてはいかがでしょうか。