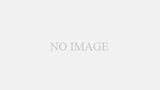印鑑証明書は、不動産登記や商業登記などさまざまな手続きで使われる書類であり、税理士業務においても馴染み深いものです。とはいえ、その交付費用を経理処理する際、「どの勘定科目にするのが適切か?」と迷うこともあります。
本記事では、印鑑証明の費用処理について、勘定科目の選び方や消費税区分の考え方、さらには税理士登録にまつわる裏話も交えて解説します。

印鑑証明とは
市町村・登記所に登録している印鑑が「実印であると証明する」書類のことを印鑑証明書といいます。
書類に実印だけ押してもほとんど効果が無く、印鑑証明書を添付することによって公に実印だと認められ効果が発揮されるます。これは「自分だけのハンコです」と公的に証明してもらう制度ということです。
不動産登記や商業登記、自動車の登録や名義変更等色々な場面で使います。
印鑑証明の費用処理:仕訳と勘定科目
印鑑証明書の交付手数料は、「支払手数料」あるいは「租税公課」などで処理されることが多いようです。
個人的な意見としては、租税公課は税的な性格のものだけを集計しておいたほうが、法人税申告書などを作成しやすく、管理もしやすいので、「支払手数料」のほうが好ましいと考えます。(もちろん、様々な意見や事情がありますから、あくまで参考として)
なお、行政サービス手数料ですので消費税区分は「非課税」となりますから、そこさえ抑えておけば大きな問題にはならないでしょう。
税理士登録時にも必要?ちょっとした裏話
税理士は、「税理士登録」が必要なのですが、その際に実務要件を証明するため、お世話になった(つまり勤務をしていた事務所の所長である)税理士に印鑑証明を貰う必要があります。
私も登録の際に、お世話になった税理士さんに印鑑証明を出していただきました。
この人は、きちんと実務経験を積んでましたよ、と証明していただくわけです。その証拠に印鑑証明をつけてもらう。
今はそんなことはないでしょうが、むかしは印鑑証明を出し渋る税理士もいたと聞きます。(根も葉もない噂話かもしれませんが)、興味があれば顧問税理士さんに聞いてみると面白いかもしれませんね。
まとめ:実務処理の注意点
一般的には支払手数料や租税公課で処理。
消費税が非課税取引となることに注意。