相続財産に土地が含まれている場合、その評価の正確性は相続税申告において非常に重要です。その際によく登場するのが「公図(こうず)」という資料です。しかし、公図は一般にはあまり馴染みがなく、「そもそも何のために使うのか?」「評価とどう関係があるのか?」と疑問を抱く方も少なくありません。
この記事では、公図の定義や取得方法、相続税評価における実務的な役割や限界について、専門知識がない方にもわかりやすく解説します。
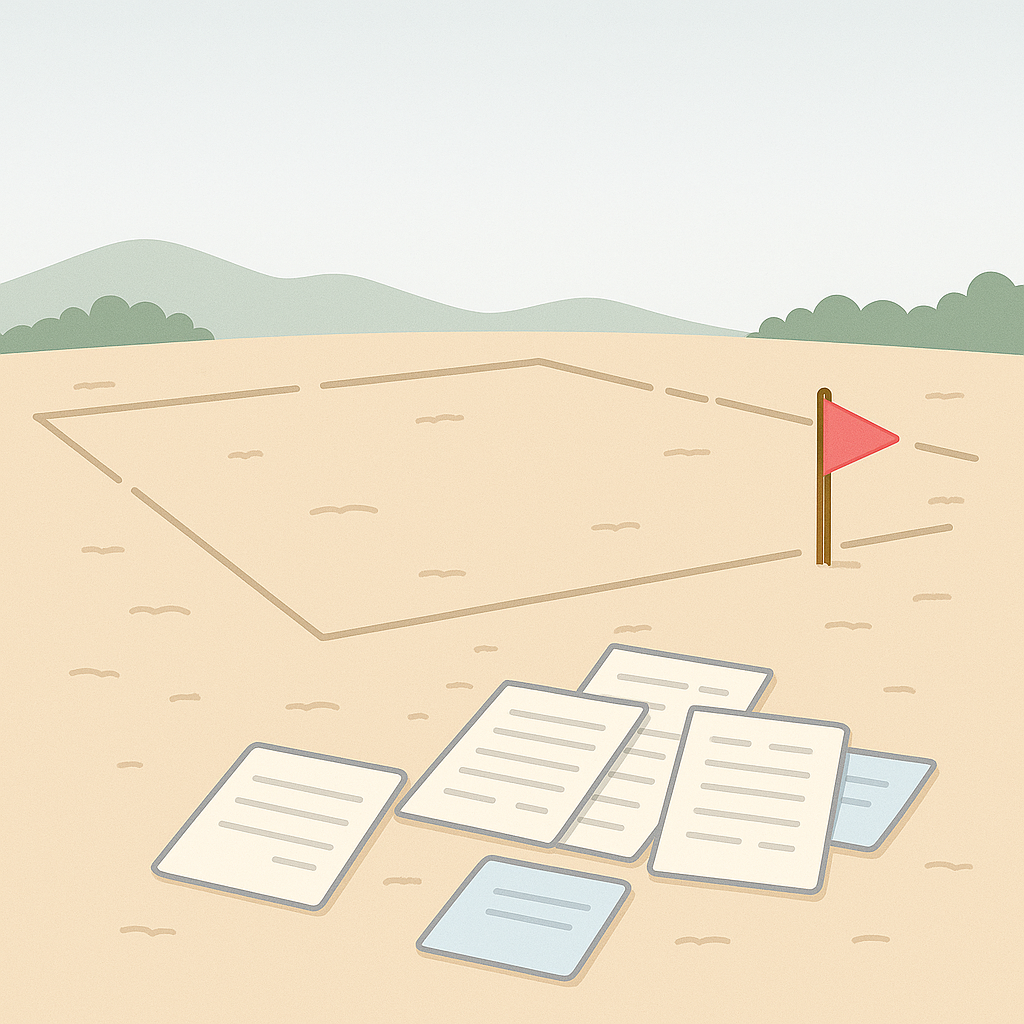
相続税評価における「公図」の役割とは?
相続財産の中に土地があると、評価明細書をつけることになります。
相続税申告書は外観性を重視しているので、財産評価についての詳細は評価明細書に記載するルールだからです。
とくに土地は個別性が強いので、添付資料などが多くなりがちなのですが、その際に「公図」と呼ばれる資料を添付することもあります。
そもそも「公図」とは何か?──法的な定義と取得方法
不動産関係の仕事の方は「公図」をご存知ですが、一般の方にはほとんど馴染みがありません。
予備知識無しに見ても、あまりよくわからないというのが率直なところです。
法務局には「地図」が備え付けられていて、正確には不動産登記法第14条第1項に規定される図面をいいます。これは、土地の面積や距離、形状、位置についての正確性が高いものだとされています。
上記の「地図」に準ずる図面のことを「公図」と呼んでいます。地籍調査などが進んでいない地域では、「地図」を備え付けられないので、明治時代に利用されていた資料を元に作成されたものを「公図」と呼んでいます。
法務局(登記所)で取得可能ですので、窓口で申請しても、ネットや郵送でも取得可能です。
相続税評価における公図の位置づけは?
公図は地籍調査などが進んでいない地域で大まかな内容を知るために備えられているものですから、絶対的に正しいとは言えないのですが、相続税評価のためには参考資料として添付することもあります。
主には、土地の位置関係などを確認します。
都市部から離れたところにある土地だと、所有者本人も状況をきちんと把握してないことも多くありますから、調べる際の「取っ掛かり」としては使えなくもない。歯切れが悪いですが、そのくらいの精度のものです。
もちろん、実地に確認したり他の資料を収集して、総合的に判断することにはなりますが、その中の一つという位置づけです。
公図の限界と注意点
あくまで公図は、正確な地図などがない場合に推測するための資料の一つです。
明治時代に利用されていた台帳をベースに作っているので、その当時の測量技術などは今と比べてもかなり劣りますし、正確な地図を作ろうという意図で作成されたものでもありませんので。
ただ、「位置関係」や「過去に水路があったのかな」とか、「里道があったようだ」みたいなことは何となく分かるので、見てみると面白くはあります。
そんな位置づけですから、極めて正確な地図などが他にあれば、特に利用する必要もないということになります。


