「住宅は資産にならない」という意見がありますが、本当にそうでしょうか?
持ち家は、老後の住宅費負担を軽減し、インフレにも強い「守りの資産」として機能します。
もちろん、株式や預貯金とは特性が異なるため、資産形成の一環として住宅を活かすには“うまく使う”視点が必要です。
本記事では、「住宅取得は資産形成になるのか?」というテーマを、老後資金・インフレ対策・現金や株式との違いを交えて、税理士の視点で整理します。

この記事は共働き夫婦の資産形成をテーマにしたシリーズの一部です。
全体像をおさえてから読み進めたい方はこちらの記事を先にどうぞ

「住宅=負債」説は人を選ぶ
資産=キャッシュアウトを減らすもの
住宅取得(持ち家)は、メンテナンス費用や固定資産税が発生するため「お金が出ていくもの=負債」と考える人がいます。
ただ、自宅(持ち家)は、家賃などの住宅費支出を軽減することも事実ですから、キャッシュアウトを減らすもの=資産であるとも言えます。
結局のところ、住宅=負債となる人はすべての人ではなく、少なくとも老後の住処がない人は資産としての性格が強いでしょう。
持家でなくてもよい属性の人
反対に、相続などで住宅が手に入る人や、収入の大きな職業などに就いている人は持家を持たなくてもよく(持とうと思えば可能なため)、そのような人たちにとっては、負債と見えるのでしょう。
ですから、一般的な属性の人は住宅取得は資産となりますから、資産形成にもなるし、ベターな選択肢です。
持家が“守り”の資産になる理由
「老後の生活」にとって重要
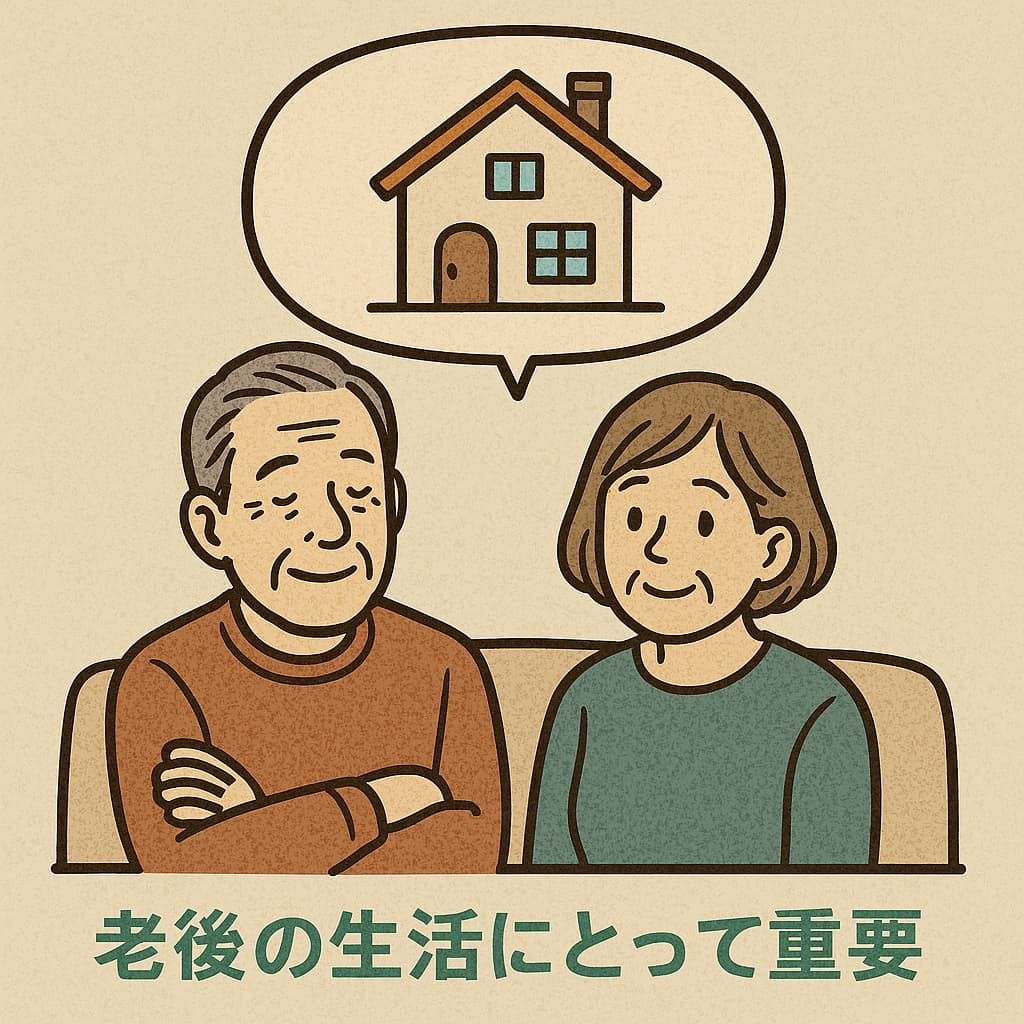
持ち家は「守り」の観点から重要な位置付けです。持家はローン返済が終われば、メンテナンス費用や固定資産税のみの支出です。
ゼロになるわけではありませんが、賃貸物件と違って住宅費が大幅に減少しますから、老後の生活においては、極めて有効です。
「現物資産」としてのメリット
また、「現物資産」であることも強みです。
経済状況がインフレ傾向にあるときは、預貯金は価値が目減りしてしまいますが、現物資産は目減りしづらい、という特徴があります。
住むことを前提にしていますから、自宅を売却することは現実的ではなくても、仮に売却したら新たな家に変えられる(購入のための原資にできる)、という事実は大きな安心感です。
株式・預貯金との違い
株式や預貯金とは「特徴」が異なる
資産形成するうえで、住宅の特徴は株式や預貯金との比較で、より鮮明になります。
資産形成では、特定の資産に構成が偏ることは得策ではなく、バランスが大事ですが、それは株式や預貯金とは違った特徴があり、お互いに補完するものだからです。
株式や預貯金は、「流動性」が極めて高い(換金がしやすい)ことが大きな特徴です。ただし、株式はリスク資産であり、預貯金はインフレ耐性が低いというマイナス面もあります。
最大の効用は「住める」こと
住宅は現物資産のなかでも、売却することが難しい、つまり流動性が低いのがデメリットです。不動産の売却は手間がかかりますので、売りたくなったからといって、即座に売れるものではありません。
一方で、現物資産ですので、インフレ耐性がある。加えて、現物であるゆえの「効用」つまり住むことによる価値があります。
株式や預貯金に住むことはできませんので。
住むところがないと生きていけませんから、「住める」という効用はかなり大きなものといえます。株式や預貯金も資産形成するうえで、必要な構成要素ですが、住宅はそれらとは異なった価値を有しています。
資産として住宅を機能させる条件

住宅を資産とするためには、その価値を毀損しないようにしなければなりません。
経済的な価値としては、メンテナンスをきちんとやること。
経済状況によって住宅の価値が下がらないように、所在地の状況は重要です。交通の便、公共施設の近接度、災害への備えなど、を考慮してなるべく価値の下がらなそうな住宅を選択することが重要です。
精神的な価値としては、これは本人が満足するかどうかでしょうが、少なくとも住んでいてストレスになるようですと「住み続けられません」。
住宅は住み続けてこそ、資産としての価値がありますから、住み続けられることこそが重要です。(難しければ移転をしなければなりません。そのためには、やはり価値を担保しておくのが必要、というループです)
まとめ:住宅は“うまく使えば”資産形成の柱になる
住宅は、「うまく」使えば資産形成のが柱になりますし、できなければかなりのロスです。
「うまく」使うことは、そこまで難しいことではありませんから、「うまく」使うことを前提に、まずは住宅取得を前向きに検討することから始めてみてください。
【あわせて読みたい記事】
住宅(持ち家)は住宅費を抑える『資産』|株や預金とは違う価値を検証【基礎編①】
「税制優遇を味方につける住宅戦略−控除・贈与・相続まで」【基礎編②】
老後の家はいつ買うか?賃貸リスク・住宅寿命から見る住宅戦略【基礎編③】
住宅ローン破綻を避けるには「オーバーローン対策」が鉄則|戦略的住宅購入【基礎編④】
共働き夫婦こそ単独ローンを選ぶべき理由|ペアローンの落とし穴とは?
頭金なしで住宅を買ってはいけない理由|ローン破綻の回避策とは


