 共働き夫婦・資産形成
共働き夫婦・資産形成 資産形成で避けるべき投資3選|相談して決めると損する理由
資産形成でやってはいけない投資手法を税理士が解説。NISA投信・不動産投資・貯蓄型保険の落とし穴と、相談に頼らず成功するための判断軸を紹介します。
 共働き夫婦・資産形成
共働き夫婦・資産形成  税金・節税・資金繰り
税金・節税・資金繰り  会計・決算の基本
会計・決算の基本 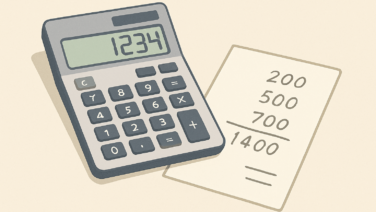 税金・節税・資金繰り
税金・節税・資金繰り  会計・決算の基本
会計・決算の基本  税理士という仕事
税理士という仕事  税金・節税・資金繰り
税金・節税・資金繰り  会計・決算の基本
会計・決算の基本  会計・決算の基本
会計・決算の基本 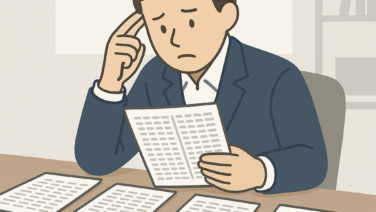 会計・決算の基本
会計・決算の基本