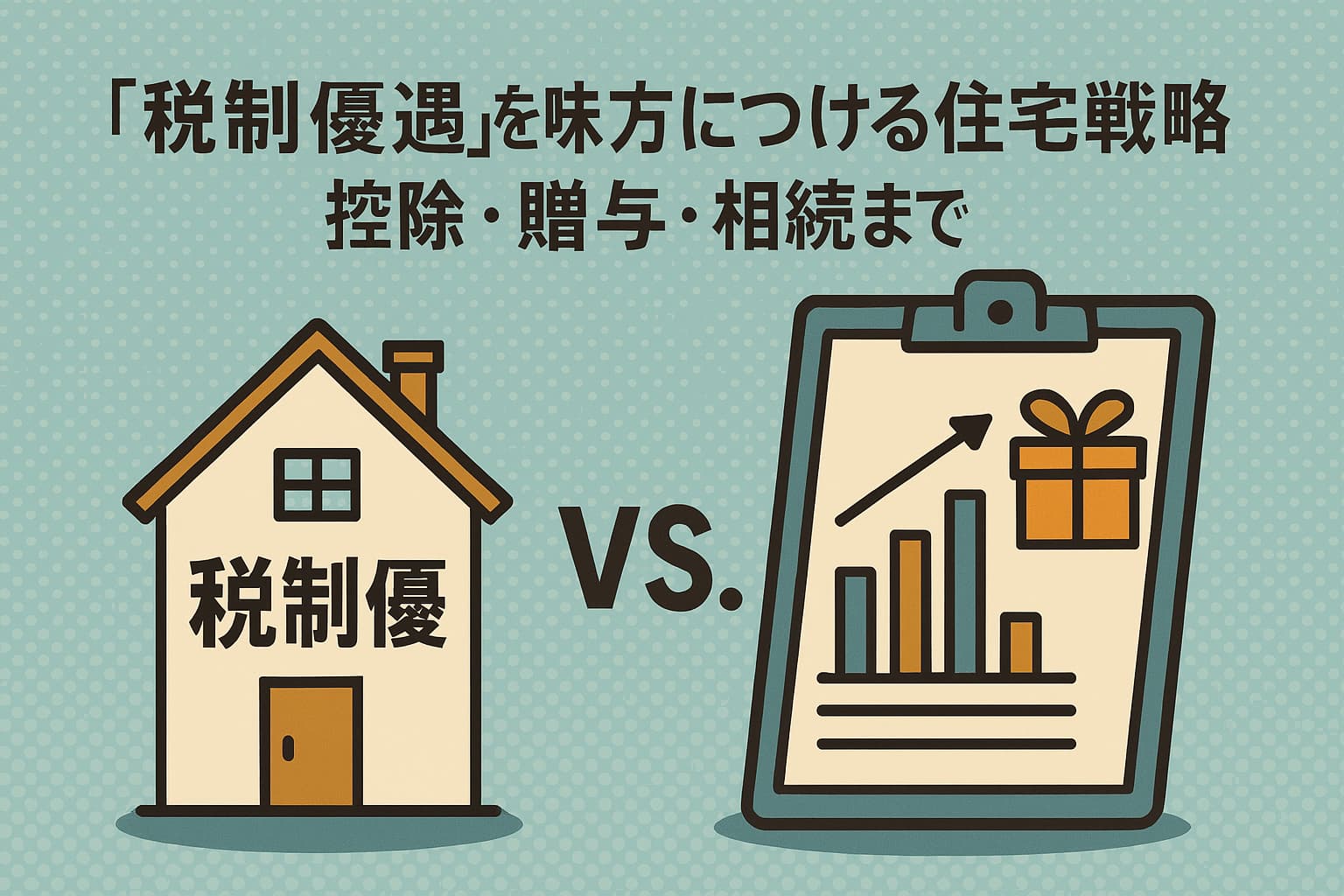住宅取得は資産形成の中心ですが、税制優遇を上手に活用することで「加速」をつけることが可能です。
これらの制度は「手続き方法」よりも、まずは全体像や活用のポイントを把握することがカギになります。
本記事では、有名な「住宅ローン控除」はもちろん、親からの援助に使える「住宅取得等資金の非課税」、意外と知られていない「新築住宅の固定資産税の減額」、さらには相続時に絶大な効果を発揮する「小規模宅地等の特例」まで、実務に通じた税理士の視点でわかりやすく解説します。
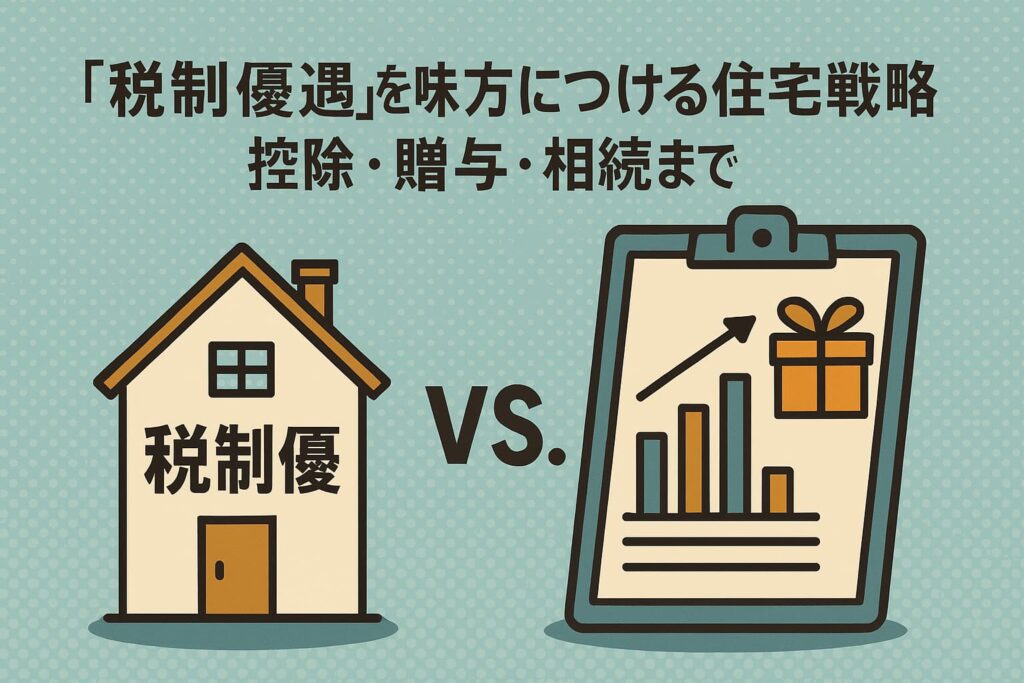
この記事は共働き夫婦の資産形成をテーマにしたシリーズの一部です。
全体像をおさえてから読み進めたい方はこちらの記事を先にどうぞ

住宅ローン控除の本質と使い方
大まかな仕組み
住宅に係る税制優遇で最もポピュラーなのは住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)でしょう。
この規定があるから、住宅はローンで買ったほうがよいと言っても過言ではありません。
住宅ローンの年末残高の1%弱(適用年によって変わります。また上限額もあります。)を所得税から控除し、所得税から控除しきれなかった一定額は住民税からも控除するという制度です。
簡単なポイントと注意点
単純計算でローン残高が3,000万円で1%の控除受ければ税金が30万円も減額されますから、住宅費の軽減にもなるし、資産形成にも「加速」がつきます。
ただし、住宅に対する制度なので、自己居住用物件で実際に居住の用に供していなければいけませんし、居住年からの適用ですから、注文住宅などは「いつ」住めるかは意識した購入計画が必要となります。
親からの資金援助を最大化する

住宅取得等資金の非課税(贈与税)
住宅取得に際して、親(直系尊属)から援助を受けるという方法にも優遇があります。
親からお金や財産をもらうと、基本的に贈与税が課税されます。
ただし、「住宅取得等資金の非課税」の制度を利用すると、贈与した金銭のうち一定額が非課税となります。(適用年によって非課税限度額が変わりますが概ね1,000万円程度です)
仮に1,000万円を親からもらうと、贈与税は約200万円ほどですが、この制度を利用すれば申告などの手続は必要なものの、税額は「0」になります。
手続きよりも他の親族への配慮が最も重要
細かな要件はありますが、一般的な住宅取得であれば要件を満たすケースが大半のため、どちらかと言えば気をつけるべきは、他の親族との不公平感などを考慮することの方が重要です。他の親族への配慮(つまり他の親族にもそれなりの金銭的な補償をするということ)がないと、親の相続の際の火種となりかねません。
また、贈与はタックスプランニングが極めて重要です(例えば精算課税を利用するのかなど)から、相続,贈与に詳しい税理士に相談することも必須でしょう。
固定資産税の優遇

新築住宅の減額
住宅を新築すると、固定資産税(建物に係る部分)が一定期間(3〜5年程度)減額されます。
固定資産税は、固定資産(土地や建物など)に課税される税金ですが、「保有」に対しての課税のため、毎年支払う必要があります。
固定資産税が一定期間とはいえ減額されるのは、住宅取得でダメージを受けた家計を回復させる一助となるでしょう。
注文住宅だと更にメリットも
固定資産税は賦課課税(行政が税額計算し納税額を通知する制度)のため、特にご自身で何かをする必要はありません(不動産取得税の申告が必要な場合がありますが大した手間ではないです)ので、勝手に減額されてる、という感じの制度です。
ただ、長期優良住宅や一般の住宅でも一定の要件を満たすと、固定資産税の減額がさらに有利に取れるので、注文住宅などであれば、建築会社と相談するのもかなり有効です。(長期優良住宅などとして知られています)
(建売だと住宅の仕様変更がほとんどできませんから、要件を満たすように住宅を変える、ということができないケースが大半です)
相続時の小規模宅地等の特例とは
相続を見据えた住宅取得をする人は少ない
住宅取得に際して、ほとんど考慮されていませんが、自身の相続に際しての相続税負担を軽減する制度もあります。
自宅敷地のような、生活基盤となる土地については一定の要件を満たすと、その相続税評価額を50〜80%減額できるという「小規模宅地等の特例」があります。
使えれば効果絶大なので「選択肢」を残す
制度の趣旨としては、生活の基盤となるような土地に多額の相続税をかけた結果、そこで暮らす家族などが、その土地を失わないように、税制優遇を図っている、というものです。
従って、その土地を相続に際して取得する人に条件があるなど、要件は厳しいですが、相続税をかなり減税できる制度なので、その含み・選択肢を残すためには、住宅取得は「かなり」有効です。(なお、この制度はマンションの敷地にも適用可能なので、住宅取得全般に適用可能といえます)
まとめ:持家の“税金効果”は見逃せない
住み心地やライフスタイルへの柔軟性は持家にも賃貸にも、それぞれ一長一短があり、どちらが優れている、といったことは断言できませんが、
税金を考慮した資産形成への寄与を考えると、持ち家に分があります。むしろ、持ち家一択でしょう。
これらの制度を「使う・使わない」よりも「知っている・知らない」によって、資金繰りや資産形成だけでなく、子供世代に引き継げる財産や手間も大きく変わりますから、制度の活用を検討すべきでしょう。
住宅取得の全体像や基本戦略をまとめた記事はこちらをご覧ください。
→共働き世帯のための住宅取得戦略−資産形成・リスク管理・老後対策の観点から
【あわせて読みたい記事】
住宅(持ち家)は住宅費を抑える『資産』|株や預金とは違う価値を検証【基礎編①】
「税制優遇を味方につける住宅戦略−控除・贈与・相続まで」【基礎編②】
老後の家はいつ買うか?賃貸リスク・住宅寿命から見る住宅戦略【基礎編③】
住宅ローン破綻を避けるには「オーバーローン対策」が鉄則|戦略的住宅購入【基礎編④】
共働き夫婦こそ単独ローンを選ぶべき理由|ペアローンの落とし穴とは?
頭金なしで住宅を買ってはいけない理由|ローン破綻の回避策とは